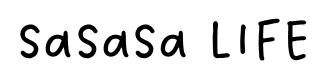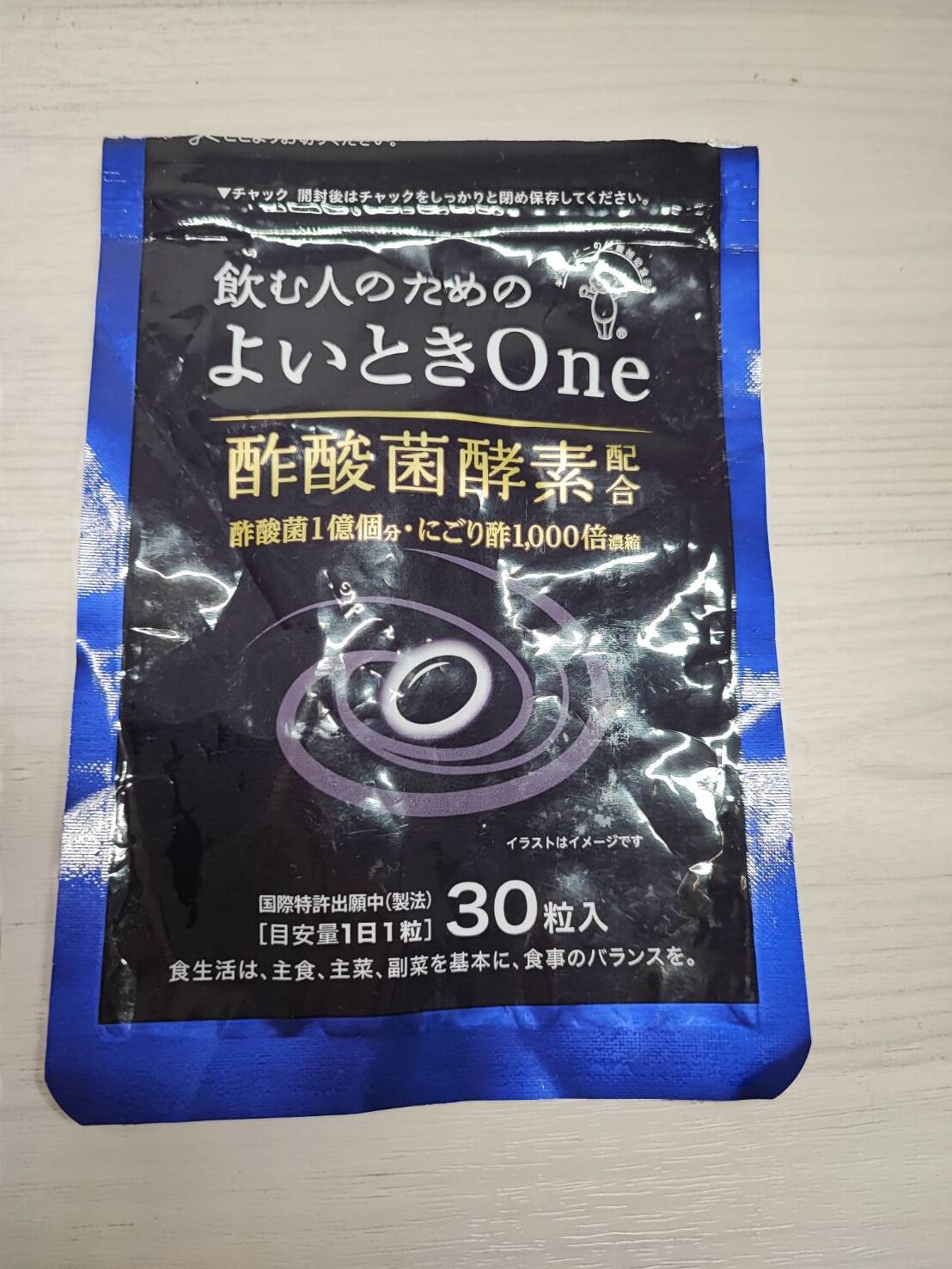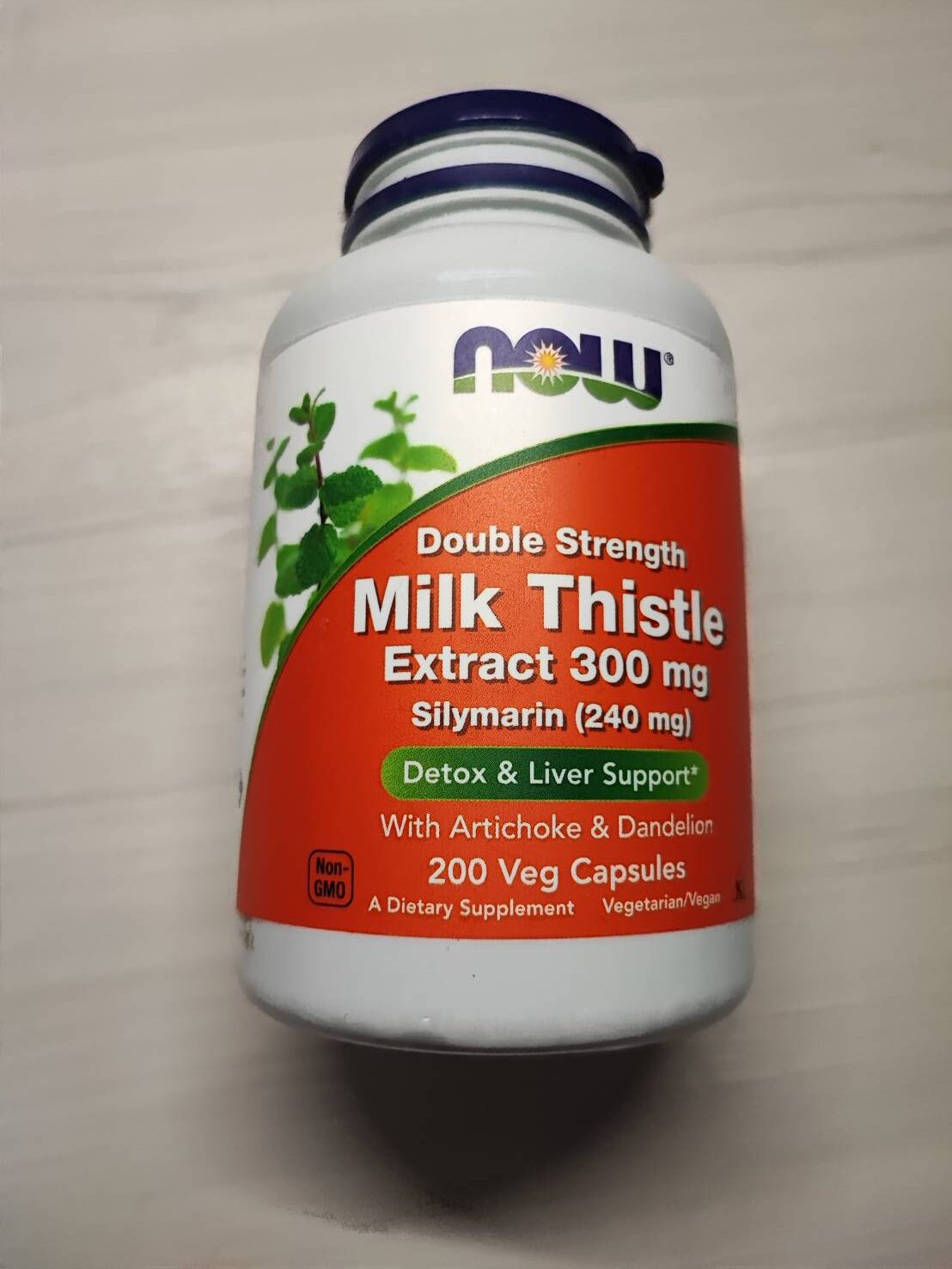「お酒を少し飲んだだけで顔が赤くなる」「ビール1杯で気分が悪くなる」──そんな経験はありませんか?実は、お酒に強い・弱いといった体質の違いは、単なる慣れではなく、生まれつきの遺伝的な要因が大きく関係しています。
とくに日本人は、お酒に弱い体質を持つ人が世界的にも多いと言われています。本記事では、アルコールが体内でどのように分解されるのか、遺伝による体質のタイプ、お酒に弱い人に共通する特徴などを詳しく解説します。
遺伝で決まっている体質
お酒に強いか弱いかは、生まれつきの体質によって大きく左右されます。とくに注目されるのが、アルコールを体内でどのように分解するかという点です。体に入ったアルコールは、まず肝臓で「アルコール脱水素酵素(ADH1B)」によって「アセトアルデヒド」という物質に変わります。このアセトアルデヒドは毒性が強く、顔の赤み、頭痛、吐き気などの原因となります。そして、次にこのアセトアルデヒドを「アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)」が分解し、無害な酢酸へと変えることで、体外へ排出されやすい状態になります。
この2段階の分解プロセスがスムーズに進むかどうかが、アルコールに強いか弱いかのポイントです。ところが、ALDH2の働きが弱い、あるいはまったく機能しない人がいます。特に日本人を含む東アジアの人々は、このALDH2の活性が低い、あるいは完全に不活性な遺伝子を持つ割合が高く、実に約4割の人が「お酒に弱い体質」、さらに約5%の人が「まったく飲めない体質」とされています。
以下の表に、日本人とその他の人種におけるALDH2の活性の有無をまとめました。
| 人種 | ALDH2活性型 | 低活性型 | 不活性型 |
|---|---|---|---|
| 日本人 | 約55% | 約40% | 約5% |
| 中国人 | 約55% | 約40% | 約5% |
| ヨーロッパ系 | ほぼ100% | ほぼ0% | ほぼ0% |
| アフリカ系 | ほぼ100% | ほぼ0% | ほぼ0% |
日本人を含むモンゴロイド系民族では、お酒に弱い遺伝子を持つ人が多く見られます。そのため、「日本人は欧米人に比べてお酒に弱い」と言われるのは、科学的にも裏付けがあるのです。したがって、自分のアルコール分解能力を理解することは、安全な飲酒生活を送る上でとても重要です。
遺伝による体質の違い全タイプ
アルコールに対する体質は、「アルコール脱水素酵素(ADH1B)」と「アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)」という2つの酵素の組み合わせによって決まります。この組み合わせは遺伝子によって決まり、生涯変わることはありません。主に次の5タイプに分類されます。
| タイプ | ADH1B(アルコール分解) | ALDH2(アセトアルデヒド分解) | 体質の特徴 |
|---|---|---|---|
| A型 | 低活性 | 活性 | 酔いやすく依存症リスクが高い。飲酒による快感が強く、翌日に残ることも多い。 |
| B型 | 高活性 | 活性 | いわゆる「お酒に強い」タイプ。酔いにくいが、飲みすぎによる疾患リスクも。 |
| C型 | 低活性 | 低活性 | 酔いやすいが不快な症状が出にくく、飲みすぎる傾向。 |
| D型 | 高活性 | 低活性 | 顔が赤くなりやすく、少量でも気分が悪くなるタイプ。 |
| E型 | 高活性 | 不活性 | 完全な下戸。ごく少量でも強い不快症状が出るため、飲酒は避けるべき体質。 |
これらの体質の違いは、両親から受け継ぐ遺伝子の組み合わせによって決まります。たとえば、両親ともにALDH2の不活性型を持っていれば、その子どももお酒を全く受け付けない可能性が高くなります。一方で、両親のいずれかが活性型であれば、子どももある程度はお酒を分解できる可能性があります。
なおこうした体質は、検査キットやパッチテストなどを活用すれば、自宅でも簡単に体質を調べることができますよ。
お酒に弱い人の特徴
お酒に弱い人にはいくつか共通した特徴があります。見た目や行動の傾向から、おおよその判断がつく場合もあるため、自分や身の回りの人の飲酒に対する理解を深める手助けになります。
まず最もよく見られるのが「顔が赤くなる」現象です。これは、体内に残ったアセトアルデヒドが血管を拡張させるために起こる反応で、専門的には「フラッシング反応」と呼ばれています。わずか1杯のビールで頬が赤くなったり、身体が熱くなる人は、お酒に対して弱い体質である可能性が高いです。
次に挙げられるのは「飲んだ後に体調を崩しやすい」ことです。吐き気や頭痛、動悸、眠気といった不快な症状がすぐに出る人は、アセトアルデヒドの分解が追いついていないと考えられます。これらの症状が起きる頻度が高い場合、無理な飲酒は避けるべきです。
体格も関係している場合があります。細身で小柄な人は体内の水分量や血液量が少ないため、同じ量のお酒を飲んでも血中アルコール濃度が高くなりがちです。そのため、酔いが早く回りやすく、体への負担も大きくなります。