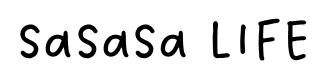「お酒は飲んでいればそのうち強くなる」と言われたことはありませんか?飲み会や付き合いの場で、「もっと鍛えれば飲めるようになる」と無理にすすめられた経験のある方も多いはずです。しかし、実際のところアルコールに強くなることは本当に可能なのでしょうか?これには、体質や遺伝、酵素の働きといった科学的な視点が深く関わっています。
本記事では、「お酒に強くなれるのか?」というテーマを中心に、アルコール耐性の5分類、飲酒によって本当に強くなる人がいるのか、酔いにくくなる方法まで、専門知識をやさしく解説します。
アルコールへの耐性5分類
アルコールへの耐性には明確な個人差があり、その背景には主に遺伝子の違いがあります。特に日本人をはじめとする東アジアの人々には、お酒に弱い体質の人が多く見られます。人間のアルコール代謝能力は、体内で働く2つの酵素の働きによって決まります。ひとつは「アルコール脱水素酵素(ADH)」で、もうひとつが「アセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH2)」です。このALDH2の活性によって、アルコールに対する強さが大きく分類されます。
以下の表は、一般的に知られているアルコール耐性の5つのタイプを整理したものです。
| 分類名 | 遺伝子型 | 特徴 | 飲酒への影響 |
|---|---|---|---|
| NN型(活性型) | ALDH2が活性 | アルコール分解が早く、酔いにくい | 顔が赤くならず、飲酒に強い |
| ND型(不活性型) | ALDH2が部分活性 | 酵素の働きが中程度 | 少量で顔が赤くなることがある |
| DD型(非活性型) | ALDH2が非活性 | 分解が極めて遅い | ごく少量でも酔いやすく、健康リスクが高い |
| 軽度ND型 | ND型の中でやや活性あり | 比較的アルコールに慣れやすい | 飲めるが、注意が必要 |
| 重度ND型 | ND型の中でも活性が弱い | 弱いながらも飲酒は可能 | 少量の飲酒でも不調を起こしやすい |
これらの分類は、単に「飲める・飲めない」という判断だけでなく、飲酒に伴う健康リスクの指標にもなります。特にDD型の方は、少しの飲酒でもがんや肝障害のリスクが高まるとされ、注意が必要です。
こうした耐性の違いは、外見からは分かりづらいため、アルコールパッチテストや遺伝子検査などを通じて自分のタイプを知ることが、無理のない飲酒習慣を築く第一歩になります。
鍛えればアルコールに強くなるのか
「飲み続ければお酒に強くなる」と信じている人は少なくありません。実際に、以前はすぐに酔っていたのに、今ではかなり飲めるようになったと話す人もいます。では、この変化は本当に「強くなった」ことを意味しているのでしょうか?
まず知っておきたいのは、アルコールに強くなるかどうかは「遺伝子」でほぼ決まっているという点です。先述のALDH2という酵素が活性型でない場合、いくら飲んでも根本的な代謝能力は向上しません。つまり、DD型の人が飲み続けても、ALDH2が突然働くようになることはないのです。
一方、ND型やNN型の人には、飲酒習慣によって「酔いにくくなった」と感じることがあるかもしれません。これは主に以下の2つの理由が考えられます。
- 酵素ではなく、脳がアルコールに慣れただけ
アルコールの感覚に脳が鈍感になり、以前ほど酔った感覚が起きなくなることがあります。これは「耐性がついた」とも言えますが、体が処理できるアルコール量が増えたわけではありません。 - MEOSという補助経路の活性化
肝臓には「ミクロゾームエタノール酸化系(MEOS)」という補助的な代謝経路があり、継続的な飲酒によってこの経路が強化される場合があります。ただし、この仕組みは効率が悪く、副産物として有害な物質を出すリスクもあるため、安全とは言い切れません。
つまり、飲酒を続けることで「強くなった」と感じることはあっても、それは身体の代謝機能が高まったわけではなく、一時的な適応に過ぎません。むしろ、そのまま飲酒を続けることで、肝臓や他の臓器へのダメージが蓄積され、健康を害する危険性の方が高まります。
お酒に強くなるには
本来、アルコールに強くなるというのは、遺伝的に与えられた能力を超えて、分解能力を向上させることを指します。ただし、現実的にはそのような体質改善は極めて難しいため、「酔いにくくなるための工夫」を身につけることが現実的なアプローチになります。
ここでは、アルコールとの上手な付き合い方として、酔いにくくするための具体的な方法をいくつか紹介します。
- 空腹を避けて飲む
空腹時に飲酒すると、アルコールが急速に吸収されてしまい、酔いが早く回ります。あらかじめ食事をとったり、脂質やたんぱく質の多いおつまみ(例:チーズ、枝豆、焼き鳥など)と一緒に飲むことで、吸収を緩やかにできます。 - 水をしっかり飲む
アルコールは利尿作用が強く、脱水症状を起こしやすくなります。飲酒中は水もこまめに摂取することで、アルコール濃度を薄める効果があり、酔いのスピードを抑えることができます。 - ペースを意識する
短時間に多量のアルコールを摂取すると、肝臓の分解が追いつかず急性アルコール中毒の危険が高まります。30分〜1時間に1杯程度のペースを守ることで、適度な酔いを楽しみながら体への負担を抑えられます。 - 低アルコール飲料を選ぶ
アルコール度数の低い日本酒やカクテルなどを選ぶことで、摂取する純アルコール量を減らすことができます。最近では、8〜10%程度の低アルコール日本酒も市販されており、お酒に弱い方でも安心して楽しめます。 - 休肝日を設ける
肝臓には回復力がありますが、連日の飲酒では回復が追いつきません。週に1〜2日は飲まない日を作ることで、肝臓の健康を保つことができます。
あるいは、お酒対策に効くといわれるサプリメントを摂取するという手もあります。実際に酒弱の私が試してみたお酒対策サプリについては、こちらの記事も参考にしてみてください。